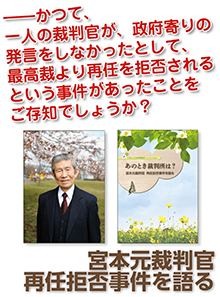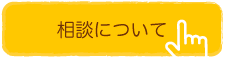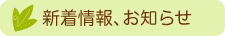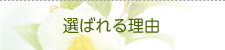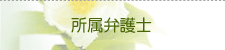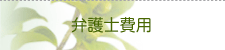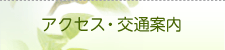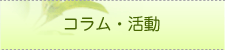コラム10:法律講座「消費者被害にあわないために」を終えて
2010.10 弁護士 松縄 昌幸
1
 さる10月2日の土曜日、当事務所として3回目となる市民講座「消費者被害にあわないために」を開催いたしました。ご来場いただいた方々には、厚く御礼申し上げます。
さる10月2日の土曜日、当事務所として3回目となる市民講座「消費者被害にあわないために」を開催いたしました。ご来場いただいた方々には、厚く御礼申し上げます。
消費者被害とは、ごく簡単にいえば、事業者(その契約に関するプロフェッショナル)と消費者(素人)との間で結ばれた契約に関する被害ということになります。そして、消費者被害ということになれば、民法では救済されない場合でも、その他の消費者保護を目的とする法律によって救済される可能性がでてきます。
いきなり消費者問題と言われても、何かピンと来ないという方も多いとは思いますが、実は我々に身近で、とても重要な問題なんです。そこで、以下では消費者問題について少しお話ししたいと思います。
2
消費者問題にはいくつかの特徴がありますが、そのうちの一つが、全ての人にとって極めて身近な問題だということです。
日常生活を送るにあたって、誰もが消費者として事業者と契約を結んでいます。例えば、家電量販店で家庭用にテレビその他の電化製品を買う場合には売買契約を結びます。また、一人暮らしや家族で暮らすためにマンションの一室を大家さんから借りる場合には、賃貸借契約を結びます。これらの契約はいずれも消費者契約にあたり、このように、私たちは日常的に多くの消費者契約を結んで生活しています。
消費者契約は私達の暮らしに身近な契約であり、その分、トラブルが生じる件数も極めて多いという状況にあります。
3
しかし、多くの人は、消費者問題といっても自分には直接関係のない問題であり、自分がそのようなトラブルに巻き込まれることはがないだろうと思っているのではないでしょうか。そこでは、そのようなトラブルに巻き込まれるのは十分な判断能力を持たない特殊な人達(例えば、ご高齢のお年寄り等)であり、普通の人間はそんなトラブルに巻き込まれることはないだろうという考えが根底にあるように思います。
しかし、私たちは日々多くの消費者契約を結んでいます。何百回、何千回、何万回と消費者契約を結ぶうちに、一回や二回はトラブルに巻き込まれる事態となる可能性は否定できません。
確かに、お年寄りの方(特に一人暮らしをされている方)は消費者被害にあいやすい傾向にあります。しかし、美容整形やインターネットオークションにおける補償をめぐる問題(落札した商品が実は偽物の場合等)など、若い人・普通の人が消費者被害に巻き込まれることも多いのです。消費者問題は、決して一部の特殊な人達だけに関係のある問題ではありません。
にもかかわらず、消費者保護のための法律についてはほとんど知らないという方が多いように感じます。例えば、クーリング・オフという言葉自体は知っているが、それがどういう制度で、どういう時に使える制度なのかはよくわからないといった方も多いのではないでしょうか。
4
消費者問題の特徴として、自分で自分を守る必要性が高いということも挙げられます。消費者被害においては、被害金額が数万円程度と比較的少額な事件が数多くあります。被害金額が少額の場合には、弁護士に依頼してみたところで、むしろ弁護士費用の方が多くかかってしまい、採算がとれずに結局赤字になってしまうということがあります。赤字になってしまうのであれば、わざわざ弁護士を頼む意味はありません。そこで、数多くの被害金額が少額な事件においては、消費者が自分自身でトラブルを解決せざるを得ないことになります(各地の消費生活センター等に相談することはもちろん可能ですし、そうするべきです)。交渉によっても問題が解決しない場合、最終的には裁判所に訴訟を提起することになりますが、弁護士でない一般市民の方が裁判所に訴訟を提起し、裁判を進めていくには大変な時間や労力が必要となります。そのような負担の大きさから、多くの方が泣き寝入りをしているのが現状でしょう。
また、被害金額が少額とは言えない場合でも、悪質な事業者(その役員を含みます)はある程度お金を集めると行方をくらませてしまうことがあります。お金を取り戻すためにはその事業者の電話番号や所在等を確認する必要がありますが、場合によってはこれが難しいということもあります。そして、これら確認ができないということになれば、お金を取り戻すことは出来ません。
このように、消費者被害にあってしまってからでは被害を回復することは難しいということがあります。結局、当たり前のことですが、そもそも消費者被害にあわないようにするという事が一番重要なのです。
5
消費者被害が社会的に深刻化するにつれて、消費者をめぐる状況は、近年大きく変化してきており、消費者保護の流れが強まっています。
消費者保護に関する法律には、基本的なものとして、「消費者契約法」と「特定商取引に関する法律」があります。「消費者契約法」は平成12年4月14日に成立し、平成13年4月1日から施行(このときから法律として効果を生じたということです)されています。そして、「特定商取引に関する法律」(もともとの名前は「訪問販売等に関する法律」)は昭和51年6月4日に公布され、同年の12月3日に施行され、その後7回にわたって改正されています(最近では、平成20年12月1日に改正法が施行されています)。また、平成21年9月1日には消費者庁が発足されました。
6
このように、現在は消費者がこれまで以上に保護される時代になってきています。しかし、悪質な事業者は法律を守りませんし、ある程度お金を集めたら行方をくらませてしまい、一切連絡がとれなくなってしまうことがあります。また、悪質な事業者でなくても、事業者がわざわざ自分に不利なことを消費者に告げないということはよくあります。事業者も自分達の生活が関係する以上、少しでも有利に事を運びたいと思うからです。そして、事業者の言うままに何も知らないで契約を結び、その契約のとおりに行動することによって、本来であればしなくていいはずの損をすることにもなりかねません。事後的な救済には限界があります。
結局は、私たち消費者一人一人が、消費者被害にあわないよう、消費者問題に関する知識によって、自分で自分を守ることが必要になります。
しかし、そうは言っても、様々な理由から、消費者問題の勉強を一から始めることは難しいという方が多いのが現実かと思います。そこで、そういった方は、消費者被害にあったのではないかと思った場合には、すぐにお近くの消費生活センター(http://www.kokusen.go.jp/map/)または弁護士に相談されることをお勧めします(依頼するかどうかは別として)。