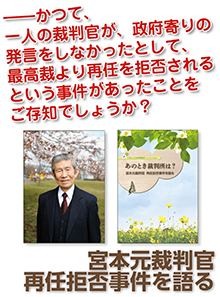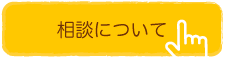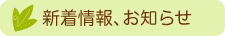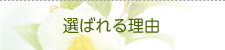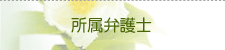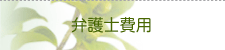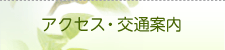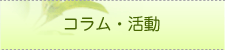相続について
- 1 遺産分割
① 相続とは
② 相続人とは
③ 相続順位について
④ 相続割合(法定相続分)について - 2 遺言書作成
① 遺言とは
② なぜ遺言書を作成するのか
③ 遺言書がない場合
④ 遺言書の種類 - 3 遺留分について
① 遺留分とは
② 遺留分のない相続人
③ 遺留分を侵害されたとき
1 遺産分割
① 相続とは
ある方が亡くなった場合に、その方と一定の親族関係にある方(配偶者、お子様など)が、財産上の権利・義務を承継することをいいます。
② 相続人とは
亡くなった方の地位を承継する方のことです。
どのような方が相続人になるかについては、民法887条~890条に、「配偶者」「被相続人の子」「直系尊属」「兄弟姉妹」と定められています。
③ 相続順位について
上記②に記載した相続人のうち、配偶者を除く方については、常に相続人となるわけではありません。次のように相続の順位が定められており、先順位の相続人がいない場合に、相続人となります。
第1順位/被相続人の子
第2順位/被相続人の直系尊属(父親、母親など)
第3順位/被相続人の兄弟姉妹
○具体的1
亡くなった方に配偶者(Aさん)と子供(Bさん)、亡くなった方の弟さん(Cさん)がいる場合には、配偶者(Aさん)と子供(Bさん)が相続人となり、弟さん(Cさん)は相続人とはなりません。
○具体例2
亡くなった方に配偶者(Aさん)と亡くなった方の母親(Bさん)、亡くなった方の妹さん(Cさん)がいる場合には、配偶者(Aさん)と母親(Bさん)が相続人となり、妹(Cさん)は相続人とはなりません。
④ 相続割合(法定相続分)について
相続人が相続財産を相続する割合です。
法定相続分として民法は、以下のように定めています。
(1)相続人が配偶者と子(第1順位)の場合
配偶者2分の1、子2分の1
(2)相続人が配偶者と親(第2順位)の場合
配偶者3分の2、親3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹(第3順位)の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
なお、子、親、兄弟姉妹が数人あるときは、相続分の中から均等分します。
2 遺言書作成
① 遺言とは
「自分の死後の財産関係を定めるための最終の意思表示」それを文書化したものが遺言書です。
② なぜ遺言書を作成するのか
遺言書を作成しておけば、原則的に遺言書の記載にしたがって相続します。
最近は、遺言書を作成される方が多くなっており、裁判所で行われる自筆証書遺言の検認件数は、毎年1万件を超えています。
遺言書を作成する理由は様々でしょうが、最も大きな理由のひとつに、自分の配偶者や子供たちが自分が亡くなった後、自分の遺した財産のことで、争うことを防止したいということがあげられます。
また、遺言書には、自分の死後、自らの財産を、誰にどのような割合で分けるかということも記載することができますので、「妻に自宅の土地、建物を遺したい」とか、「長男に一定の金融資産を遺したい」というような場合、さらには「相続人には相続させたくない(特定の団体等に寄付したい)」とお考えの場合には、作成しておく必要があります。
③ 遺言書がない場合
相続人全員で遺産分割協議(話し合い)を行う必要があります。
相続人同士の話し合いで円満に解決すればよいのですが、紛争になってしまうこともあります。
なお、相続人が不存在の場合には、一定の手続を経て国庫に入ってしまうこともあります。
④ 遺言書の種類
ア 自筆証書遺言
遺言者自らが、紙に遺言の内容の全文を書き、かつ日付、氏名を書いて、押印することにより作成する遺言。
裁判所での検認手続が必要です。
イ 公正証書遺言
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が文章にまとめ、公正証書遺言として作成するもの。
証人2人以上の立ち会いが必要とされています。
ウ 秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名、押印した上で、これを封じ、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、公証人に一定の事項を書き入れてもらい、証人と遺言者が署名することにより作成するものです。
◎それぞれの種類の遺言書には各々メリット、デメリットがありますので、特長をしっかりと理解して、作成することが重要です。
遺言書作成に関する詳細は、当事務所にご相談ください。
3 遺留分について
① 遺留分とは
一定の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。
具体的には、亡父親の遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」と記載してあり、長女に関する記載がない場合でも、長女は、一定の相続分を得ることができます。これを遺留分といいます。
② 遺留分のない相続人
亡くなった方の「配偶者」、「子」、「直系尊属」には、遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
③ 遺留分を侵害されたとき
遺留分が侵害された場合には、「遺留分減殺」を請求することにより、遺留分を確保することができます。
いい方をかえれば、遺留分は、自動的に確保されるわけではないため、必ず「遺留分減殺」を請求する必要があります。
なお、遺留分減殺請求を行うに際しては、期間の制限がありますので、遺留分が侵害されていることがわかった場合には、早めに手を打つことが必要です。
遺留分及び遺留分減殺請求に関する詳細は、当事務所までご相談ください。