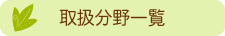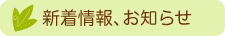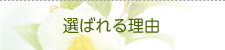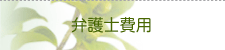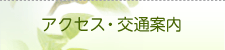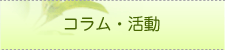万葉集の時代と多摩川
万葉集のなかでも、巻十四の東歌と巻二十などの防人の歌は、「庶民の歌」、「地域の歌」として、素朴な味わいを愛好する者は多い。
私が、朝に夕に老犬と散歩する多摩川を詠んだ歌にも、万葉の時代と庶民の生活をみることができる。
多摩川に さらす手作り さらさらに
何ぞこの児の ここだ愛しき
(巻十四-3373)
当時は、税(調)として献納するために、武蔵、筑波など各地で麻布が織られていた。「調布」「麻布」という地名にこれが残されている。織った布を白くするために川の流れにさらす。色とりどりの着物を着た女性たちが、姉さんかぶりにたすきがけで川に並んで、麻布を清流に流している。「さらす」から「さらさらに」と続く音感から、麻布がゆらゆらと水に揺れるさまと川の水が「さらさら」と流れる音を感じさせる。その多摩川の景色を見ながら、作者の心はひたすら一人の女性に向けられている。作者は、それを、「何ぞこの児のここだ愛しき」(どうしてこのこはこんなにかわいいんだろう)と歌う。「何ぞ」と「ここだ」の東国なまりが掛け合いになっていて、一気に歌える調子のよさがいい。労働の歌であり、民謡として歌われたものだという。
赤駒を 山野に放し 捕りかにて
多摩の横山 徒歩ゆか遣らん
(巻二十-4417)
防人椋橋部荒虫(くらはしべのあらむし)の妻宇遅部黒女(うぢべのくろめ)の作とある。天平勝宝7年(755年)2月、防人交替のときの武蔵国豊島郡出身の防人の妻の歌である。防人は九州・壱岐・対馬の辺境を守る兵士である。東国から徴集され、3年交替で、太宰府に送られた。遠い旅路を馬で行かせたいが、赤駒を野に放して捕らえられず、多摩の横山の道を歩いて行かせねばならないのか、という妻の嘆きの歌である。多摩の横山というのは、多摩川の西側の多摩丘陵のことだという。府中市にあった多摩の国府に集合した防人たちは、関戸橋付近から多摩川を渡って多摩丘陵をこえ、鎌倉街道を通って相模の国に入り東海道筋の足柄峠にでたといわれている。これからの長い道のりを歩いていかねばならない夫を思いやる妻の心情が、「とりかにて」と「かちゆかやらん」という東国なまりの簡潔な表現により、強く迫ってくる。